2007年10月10日 (水)に書いた「菜園たより」10月2週号アップの記事
http://nonotobira.typepad.jp/blog/2007/10/102_173d.html
で、その見出しにある「地域農業に支えられて」に関連して触れた、農水省の「農地・水・環境保全向上対策」について、以下のような記事を読みました。
http://www.nougyou-shimbun.ne.jp/modules/bulletin/article.php?storyid=977
に、一部内容が載っています。
配達のおじさんが、時々サービスで日本農業新聞を入れてくれるので、たまたま本文を読みましたが、実に「かわいそう」な話でした。
意欲的な農家が、環境保全型農業で生き抜くために、営農組合の仲間とエコファーマーの資格を取って、初年度は地域の老人会や子供会などと連携して環境美化の共同活動をして実績を積み、次年度はその補助金で有機肥料を購入して、より環境保全型を目指して行こうとしていたのに、県の財政難のため、手を上げるのが遅かったからと門前払いになった、というのです。
うちの近所の同様の活動は、どうなったのでしょう。同じような感じで成立した田んぼ関係の方々の組織が、夏に田んぼの近くの草刈りなどを共同でする、というお知らせが入っていました。この辺では、2軒、大きな「担い手」の専業農家がいらして、その1軒が、この共同事業の代表になっていました。やはり、この地で、米麦を中心として農業で生きていくうえで、この「農地・水・環境保全向上対策」に対応することが必要、と考えての動きだったと思うのです。
埼玉県の場合、ちゃんと機能しているのでしょうか。
新聞記事の最後には、東北大教授(工藤昭彦さん)の、「制度を設計した時点で地方自治体の厳しい状況は予想できたはず。環境保全が目的なら、国民にも利益になるので、税金を投入することへの反発は少ないはず。定着までの一定期間、活動組織を満遍なく支援することが重要」とのコメントを載せています。
いはゆる環境支払い、農家への直接支払いへの、国民的合意が、できているとは思えず、ほかの新聞じゃあ、こういうコメントは載らないんじゃないかと。
知人のブログで、こういうことをいっている人がいると知ったのですが、それに賛同する人が大多数なんだろうとも思うわけです。(日経とか、プレジデントとか、読んでる人、と勝手に想像する)
「コメさえつくっていれば確実に元がとれるので、非効率な兼業農家が残り、コメ以外の作物をつくらなくなったのだ。こういう補助金に寄生している兼業農家がガンなので、(中略)米価を含む農産物価格の規制や関税を全廃し、兼業農家を駆逐する必要
がある。」(池田信夫blog)
http://sanissi.exblog.jp/7577934/より引用。
農水省は、「品目横断」と、この「農地・水・環境」で、環境を保全したまま、効率よい農業を、という狙いだったのかもしれませんが、実際の農家は翻弄されるだけ、ということにならなければよいのですが。
自分たちは、翻弄の対象にもならない、超零細借地農ですが、現場はちゃんと見て行きたいと思います。
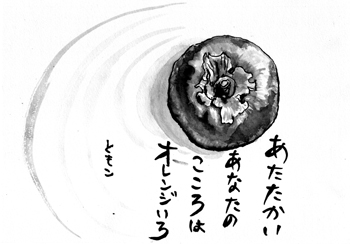







最近のコメント